2025/08/28
扇風機のしまい方は?扇風機を分解して収納する方法や掃除の仕方をご紹介

夏の間にフル稼働した扇風機。シーズンが終わる頃には、ほこりがたまっていて意外と汚れています。来年も気持ちよく使うためには、収納前に掃除をしておくのが理想です。
今回は、分解できる扇風機、分解できない扇風機、タワー型の扇風機の片付け方や掃除方法を解説。扇風機を分解する手順や掃除後の扇風機の収納方法についてもご紹介しています。
Outline 読みたい項目からご覧いただけます。
分解できる扇風機の片付け方
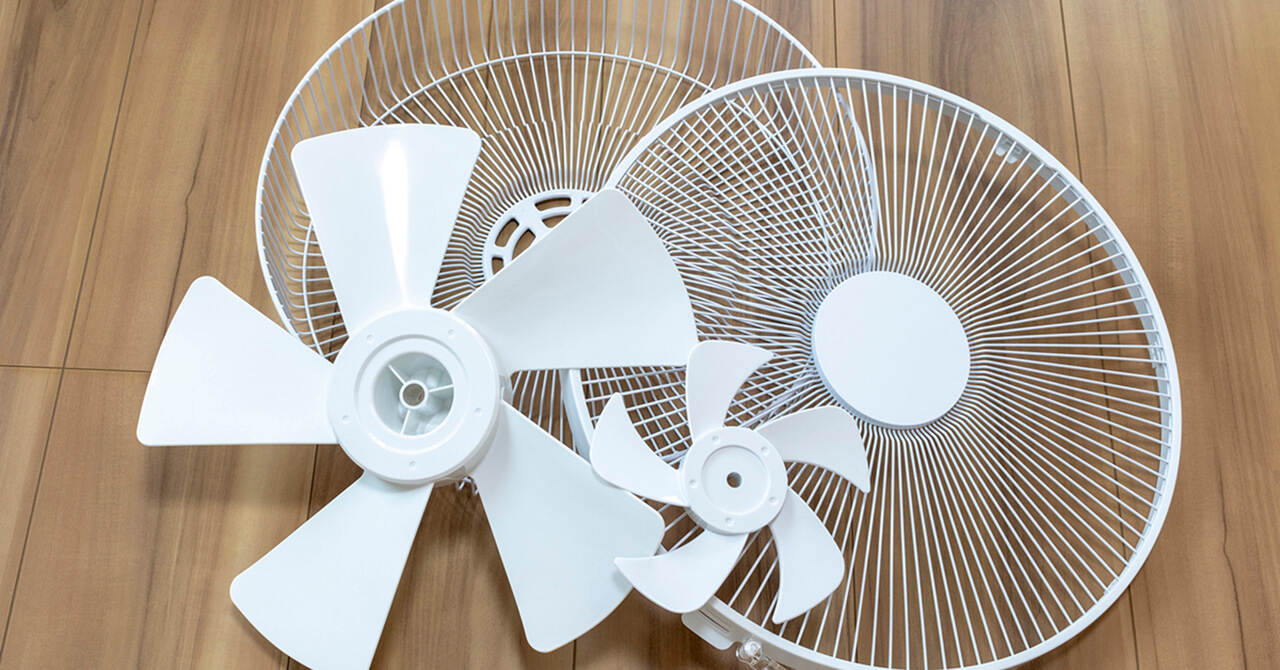
分解できる扇風機はコンパクトに収納するために分解してから収納するのがおすすめです。
分解することで、購入時の元箱に入れて収納したり、市販の衣装ケースや収納ボックスに入れて保管しておくことができます。箱に入れて収納しておけば、押入れやクローゼットのなかで何かが落ちてきても、衝撃を緩和できるでしょう。
また、元箱や収納ケース・ボックスに入れることで、別の荷物と重ねて収納することができるため、デッドスペースができにくいというメリットもあります。
扇風機を分解する手順
分解できる扇風機は、掃除や収納がしやすいように分解しておきましょう。
※メーカーやモデルによって構造が異なります。必ず、お持ちの扇風機の取扱説明書に目を通してください。
電源を切ってコンセントを抜く

扇風機の分解を始める前に、電源が切れていることと、コンセントが外れていることを確認しましょう。コンセントを差し込んだまま作業をしてしまうと、分解中に誤って電源を入れてしまう恐れがあります。
ケガや故障につながる可能性もあるため、作業を始める前に必ず電源とコンセントをチェックしましょう。
扇風機の前カバーを外す
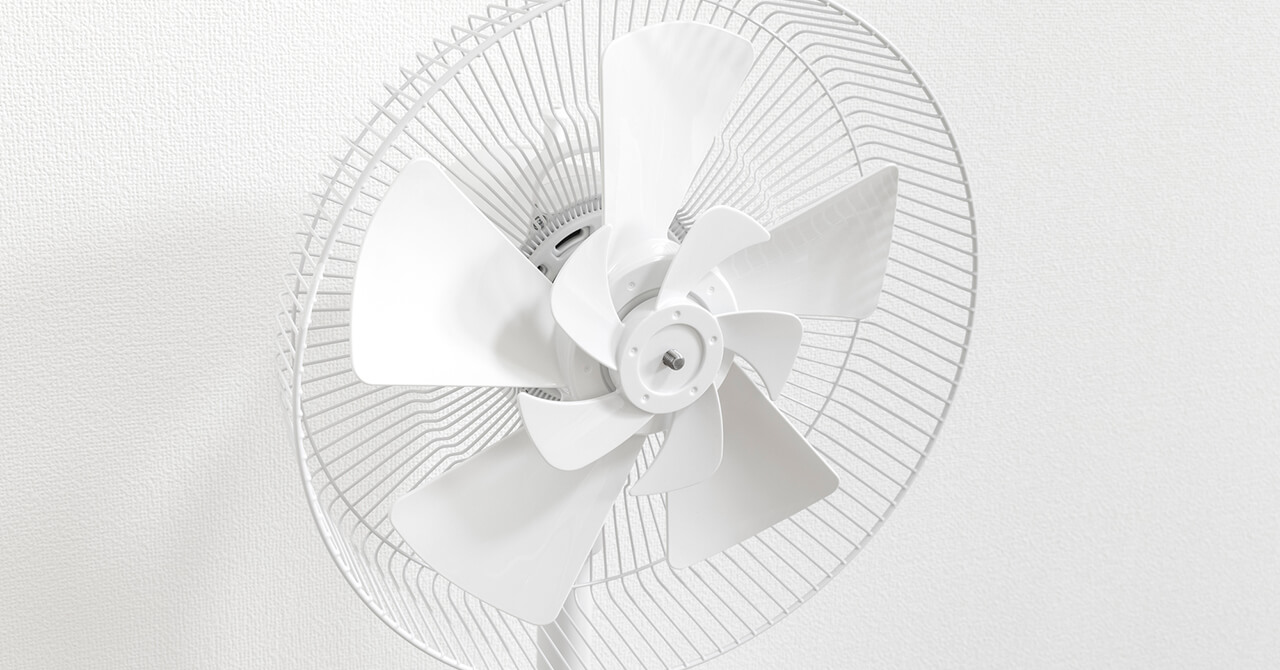
扇風機の前面に付いている前カバーを外しましょう。
クリップで固定されているタイプが主流です。クリップが折れてしまわないように、力を入れすぎないよう注意が必要です。
扇風機の羽根(プロペラ)を外す
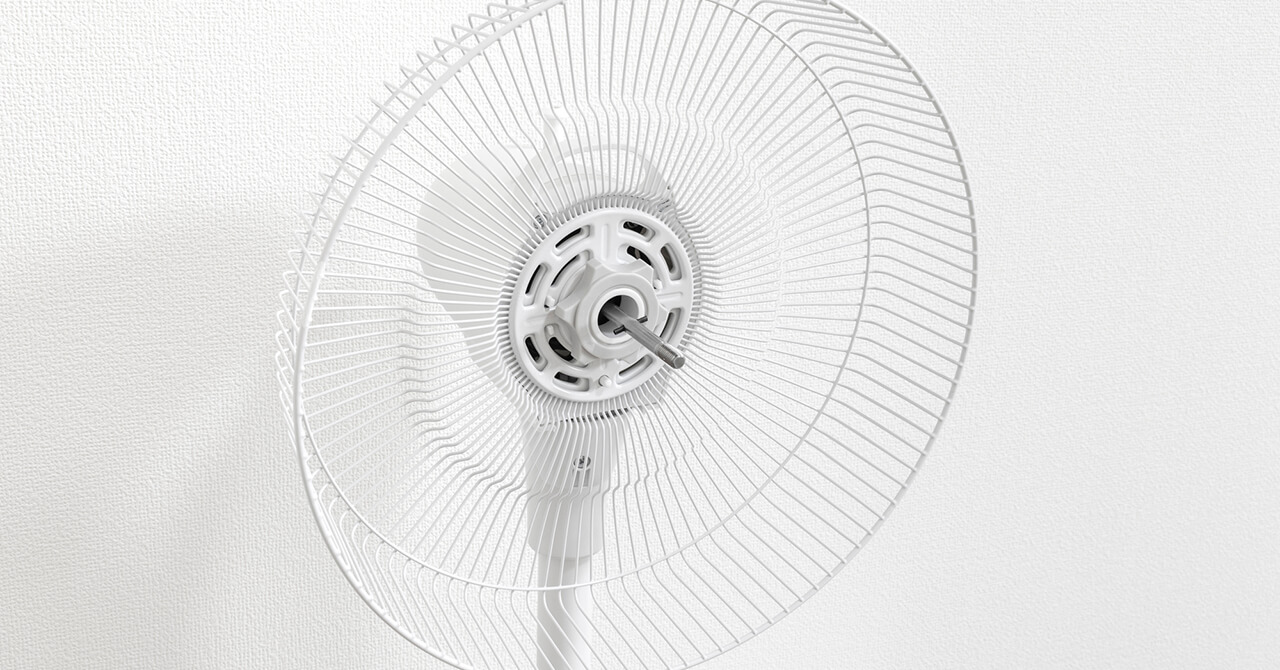
前カバーを外したら、羽根(プロペラ)を外します。正面に付いているキャップを回して外すことで、羽根(プロペラ)部分を取り外すことができます。
扇風機の後ろカバーを外す

次に、扇風機の後ろカバーを外します。羽根が付いていた後ろ部分にネジを回して外せば、後ろカバーを取り外すことができます。
支柱と台座を分解する

扇風機によっては、支柱と台座も分解可能です。支柱と台座を分解できれば、元箱や収納ボックスに入れやすくなります。
分解できる扇風機の掃除方法
扇風機は一見きれいに見えても、汚れやほこりがたまっています。分解した後は、収納前に掃除をしましょう。掃除せずに収納してしまうと、汚れが取れにくくなったり、故障の原因になってしまう恐れがあります。
次は、扇風機の掃除の仕方についてご紹介しますので、参考にしてみてください。
掃除機でほこりを吸い取る
まずは、扇風機についているほこりを掃除機で吸い取ります。とくに、風を送る部分の羽根(プロペラ)やカバーは、ほこりがたまりやすいので、重点的にやりましょう。
掃除機がない場合は、ハンディモップ、軍手、ハケなどでもほこりを落とせます。
水ぶきする
ほこりを取ったら、クロスで羽根(プロペラ)やカバーを水ぶきします。
羽根(プロペラ)やカバーは水洗いできるので、ほこりや油汚れなどがこびりついている場合は、中性洗剤を使ってスポンジで洗いましょう。
中性洗剤を使って洗った後はシャワーですすいで、クロスで水気をふき取りましょう。
パーツを乾かす
洗った後の羽根(プロペラ)やカバーは、風通しの良い場所でしっかりと乾燥させましょう。
パーツを乾かしている間に本体を掃除していくと効率よく掃除が進められます。
本体と電源コードの汚れをふき取る

本体と電源コードは、ほこりを取ってからクロスできれいにふき取ります。
扇風機を操作するボタンの部分は人の手がよくふれてる部分。手あかなどが気になる方は、家電用の除菌シートでふくといいでしょう。
ほこり防止をする
柔軟剤を使って、羽根(プロペラ)やカバーにほこりをつきにくくすることができます。柔軟剤をクロスになじませて、羽根(プロペラ)やカバーを拭いていきましょう。
柔軟剤で仕上げることで、静電気防止になり、ほこりがつきにくくなります。
分解後のパーツの保管方法
扇風機を無事に分解できたものの、「外したネジや部品を、どうやって保管すればいいんだろう?」と悩むことはありませんか。
適当にまとめてしまうと、来シーズンいざ組み立てようとした時に「ネジが1本足りない!」「羽根に傷がついてる...」なんてことになりかねません。
ここでは、分解した各パーツを安全に保管し、紛失を防ぐための具体的な方法とコツをご紹介します。
なくしやすい「ネジ・小さな部品」の保管術
扇風機の組み立てで最も困るのが、ネジなどの小さな部品の紛失です。これらをなくさないためには、以下の方法が非常に効果的です。
- ジッパー付きの小さな袋に入れる
チャック付きのポリ袋に、外したネジやワッシャーなどをすべてまとめて入れ、しっかりと口を閉じましょう。こうすれば、バラバラになる心配がありません。 - 袋に名前を書く
袋には油性ペンで「扇風機のネジ」と書いておくと、他のものと混ざらず、一目で何かわかります。 - 本体にテープで貼り付ける
まとめた袋を、扇風機の台座の裏やモーター部分など、目立たない場所にマスキングテープで軽く貼り付けておくのもおすすめです。こうすれば、部品だけ別の場所にいってしまうのを防げます。
リモコンや説明書は一か所にまとめる
本体はあっても、リモコンや説明書が見つからないのも「あるある」な失敗です。来年にそんな失敗を防ぐために以下の対策をやっておきましょう。
- 本体と同じ袋・ケースに入れる
リモコンと取扱説明書は、必ず扇風機本体と一緒の収納ケースや段ボールに入れることを徹底しましょう。 - リモコンの電池は抜いておく
液漏れによる故障を防ぐため、リモコンから電池を抜いておくのを忘れずに。抜いた電池は、リモコンと一緒に小さな袋に入れておくと良いでしょう。
これらのパーツを丁寧に管理することで、来年の夏もスムーズに扇風機を組み立て、気持ちよく使い始めることができます。
分解できない扇風機の掃除の仕方
分解できない扇風機もできる範囲で掃除をして、きれいにしてから片付けましょう。
基本の掃除方法
扇風機が分解できないとき、シーズン中に簡単な掃除をしたいときは、こちらの方法をお試しください。
ほこりを取り除く
扇風機の電源を切り、コンセントを抜いたら、ハンディモップを使ってカバーや本体のほこりを取ります。
1cmのさいの目状に切り込みを入れたスポンジを使うと、カバーのほこりが取りやすくなります。
落ちにくい汚れはふき取る
落ちにくい汚れを見つけたら、クロスでふき取りましょう。手あかなどが気になる場合は家電用の除菌シートでふき取ります。
タワー型の扇風機の掃除方法
タワー型の扇風機は、分解できないので内側にあるパーツを直接掃除することはできません。
無理に分解してしまうと故障の原因となってしまいます。外側のみできる範囲で掃除をしましょう。
吸気口のほこりを取る
扇風機の電源を切り、コンセントを抜いたら背面にある吸気口のほこりを掃除機で吸い取ります。吸気口のフィルターが取り外せる場合は外して、水洗いできるものであれば水洗いしましょう。
吹き出し口のほこりを取る
正面にある吹き出し口のほこりを掃除機で吸い取ります。細かいところにつまったほこりは、掃除機のブラシタイプのノズルか綿棒を使って取りましょう。
拭き掃除をする
本体や電源コードはクロスできれいに拭きます。ボタンなど操作する部分の手あかが気になる方は家電用の除菌シートで拭きましょう。
扇風機の収納アイテムをタイプ別にご紹介

こちらでは扇風機のタイプ別におすすめの収納アイテムをまとめました。「購入時の箱を捨ててしまった」「選び方がわからない」という方は参考にしてみてください。
分解できる扇風機に使える収納アイテム
分解してコンパクトに収納できるタイプは、アイテム選びの幅が広がります。
- 扇風機専用の収納ケース
内部にクッション材が入っているものなら、パーツ同士がぶつかって傷つくのを防げます。持ち手付きを選べば、持ち運びも楽になります。 - 透明な衣装ケース
中身が見えるので、来シーズン取り出すときに一目瞭然です。ケースの中でパーツがごちゃごちゃにならないよう、小さな仕切りを使うとスッキリ管理できます。 - ジッパー付きの大きな収納袋
不織布などの通気性が良い素材でできた袋は、ほこりをしっかり防ぎつつ、使わないときは小さく畳めるので便利です。省スペースを重視する方におすすめ。
分解できない扇風機に使える収納アイテム
一体型や、分解が難しいデザインの扇風機は、そのままの形で保管する必要があります。
- 立てたまま収納できる扇風機カバー
上からすっぽり被せるだけで、ほこりや日焼けから本体を守ってくれます。おしゃれなデザインのものを選べば、部屋の片隅に置いてもインテリアの邪魔になりません。 - 家具の隙間に入る収納袋
クローゼットやベッドと壁の隙間など、デッドスペースを有効活用できる縦長の収納袋です。 - キャスター付きの収納ラック
押入れの下段などに収納する場合、キャスター付きのラックに乗せると、重い扇風機も簡単に出し入れできます。
タワー型扇風機に使える収納アイテム
タワー型は、縦長の専用カバーをかけてほこり対策をして、カバーをかけてクローゼットの隙間に立てかけておきましょう。生活空間に置く場合は、デザイン性の高いカバーをかけて目隠しをすると、生活感を抑えられます。
扇風機の収納場所はどうする?

こちらでは自宅で扇風機の収納場所として活用できる場所をご紹介しています。収納場所がないという方は、思い切って扇風機を出しっぱなしにするという選択肢もあります。
クローゼット・押入れにしまう
扇風機を次のシーズンまで長期的にしまっておく場合は、押入れやクローゼット、ロフトなどを選ぶ方が多いことでしょう。
このとき、扇風機のカビ対策として湿気を避ける工夫をしておくことを忘れないでください。対策方法としては除湿剤を置いたり、定期的に換気をしたりするのがおすすめです。
また、扇風機などの季節家電は、長期間保管しているうちに収納スペースの奥の方に押し込まれてしまいがち。スムーズに出し入れするためにも、キャリー付きの台座に載せて収納するのがおすすめです。
ベッド下・家具の隙間にしまう
ほこりが溜まりやすい場所なので、必ず収納袋やケースに入れましょう。
また、カバーに入れたとしてもカバーがほこりだらけにならないように定期的ベッド下や家具の隙間を掃除することも忘れずに。
思い切って扇風機を出しっぱなしにする
あえて扇風機を収納せず、リビングなどで活用する方法もあります。
扇風機と言えば夏を過ぎたら使わないイメージですが、それ以外のシーズンでも活用可能です。たとえば、冬場に暖房を使う際、扇風機で天井に向かって送風すると部屋全体を効率よく暖めることができます。
また、洗濯物を部屋干しする際に扇風機で風を当てておけば、生乾きを防いで効率よく乾燥させることができます。
居住スペースを圧迫してしまうのが難点ですが、収納スペースが十分に確保できない場合は収納せずに活用してみるのも一策だと言えます。
扇風機などの季節家電はトランクルームでの収納がおすすめ

扇風機の収納方法をご紹介してきましたが、収納スペースに余裕がないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。とはいえ、季節外れの扇風機を部屋の片隅に置きっぱなしにするのは不格好です。
そのような場合は、トランクルームでの収納を検討してみてはいかがでしょうか。
トランクルームとは、月額制で収納スペースをレンタルできるサービスのこと。トランクルームには、扇風機以外にもさまざまなアイテムを保管しておくことができ、便利な収納スペースです。
たとえば、ヒーターや電気カーペットなどの季節家電を預けておけば、季節ごとにスムーズに家電を入れ替えることができるでしょう。
また、衣替えした洋服や、年に数回しか使わないレジャーアイテム、普段見返すことがない思い出の品等を預けておけば、自宅スペースを快適かつ利便性の高い空間に保つことができるでしょう。
扇風機の収納に関するQ&A
最後に、扇風機の収納時におさえておきたい情報をQ&A形式でご紹介します。
扇風機を横置きで収納するのはOK?
基本的には横置きで扇風機を収納するのは推奨されません。羽根やガードといったパーツが変形したり、破損したりするリスクがあるからです。
ただし、例外として以下の場合は横置きでも問題ありません。
- 分解して元箱に戻す場合
メーカーが安全な梱包方法として設計しているため、元箱の通りに収納する分には大丈夫です。 - 分解して専用のケースに収納する場合
: 羽根やガード、モーターなどのパーツをそれぞれ分けてケースに平置きするなら、破損の心配はほとんどありません。
分解できない一体型の扇風機は、立てたままの状態で保管するのが最も安全です。
どうしても横置きにする場合は、羽根やガードにクッション材を挟むなど、保護をしっかり行ってください。また、上に重いものを重ねないように注意しましょう。
扇風機のリモコンは電池を入れっぱなしでもいい?
扇風機のリモコンは必ず電池を抜いてから収納・保管しましょう。 長期間、リモコンの中に電池を入れたままにしておくと、液漏れを起こす可能性があり、リモコンの故障につながります。
液漏れした液体が内部の基盤や端子を腐食させてしまうと、来シーズンに新しい電池を入れても動かなくなることがあります。
来年の夏、気持ちよく扇風機を使い始めるためにも、収納前には必ずリモコンから電池を抜き、本体や収納ケース内の小物ポケットに一緒にしまっておきましょう。
コードを扇風機本体に巻きつけてもいい?
収納時にやりがちなのが、電源コードを扇風機本体の首(モーター部分)にきつく巻きつけてしまうこと。これは収納時のNG行為です。
コードの根元に強い負荷がかかり、断線や接触不良の原因になります。来シーズンに使おうと思ったら「電源が入らない...」なんてことにもなりかねません。
コードはふんわりと円を描くように束ね、結束バンドやマジックテープ、または製品に付属していたコードホルダーを使って軽くまとめましょう。
まとめ
今回は、扇風機の収納方法や収納前の掃除の仕方、トランクルームを活用した収納についてご紹介しました。
扇風機をはじめとした季節家電は、シーズン以外は長期間保管しておくことになるため、収納スペースを圧迫する原因になりがちです。
今回ご紹介した情報を参考に、トランクルームでの収納を検討してみてはいかがでしょうか。
もっと知りたい!
続けてお読みください
![TRUNKROOM MAG[トランクルームマガジン]-モノとうまく付き合う情報サイト](/mag/assets/img/common/logo-01.svg)




















